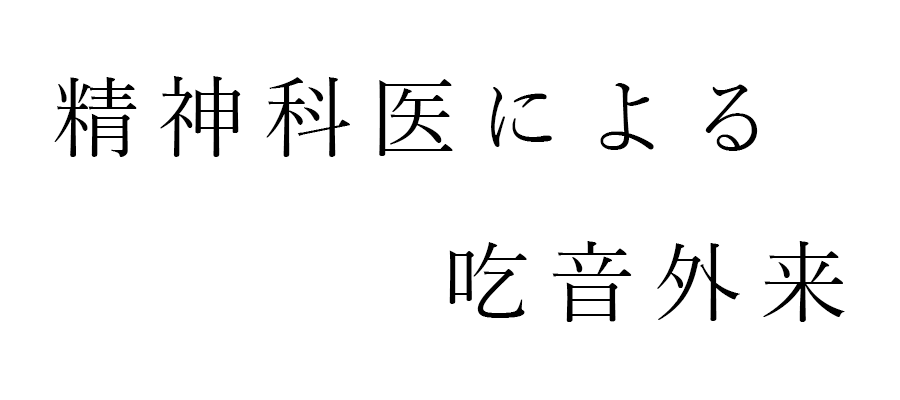
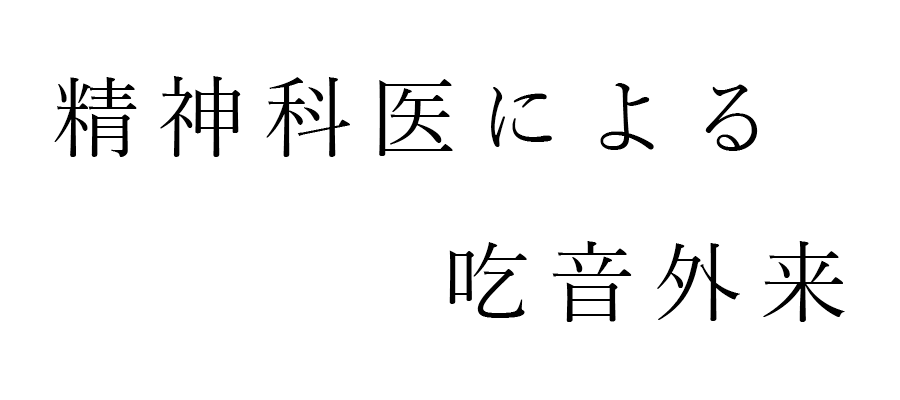
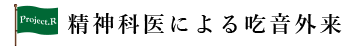
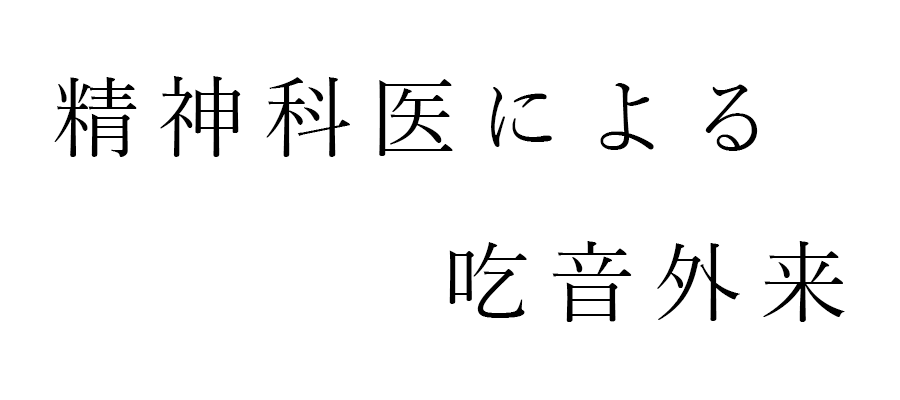
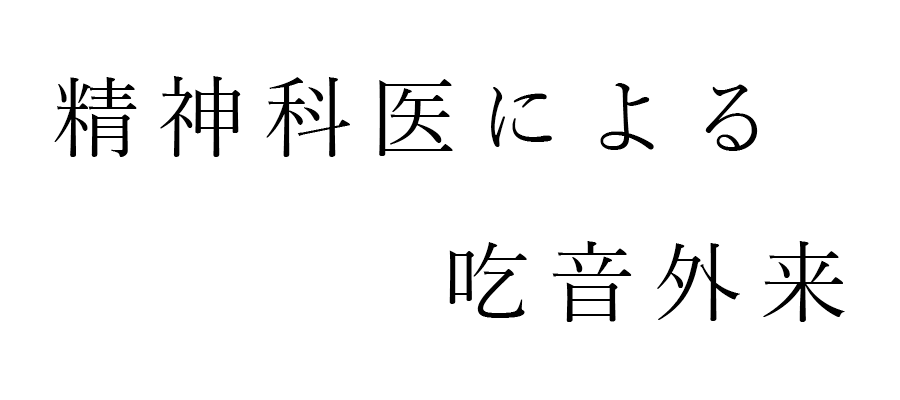

���쌫��@�`�v���t�B�[���`
���_�ی��w���B1962�N���܂�B1991�N�M�B��w��w�����ƁB�M�B��w��w�����_��w�������ǁA����a�@�i���쌧���{�s�j�Ζ����o�āA2000�N���獲���a�@�i�啪���啪�s�j�Ζ��B2018�N2���Ɂu�h���O���v�J�݁B
| 1�j�l�����_�o�����h���F | �]������_�o�����Ȃǂɂ��]������ɔ��� |
|---|---|
| 2�j�l�����S�����h���F | �S�I�O���Ȃǂ̐S���I�v�����������Ŕ��� |
���@�ł́u�Ԑږ@�v�Ƃ����h�����Ö@���s���Ă��܂��B
���Ԃ��|���Ȃ��班�����h���̍��{�I�ȉ��P��ڎw���܂��B
�i�X�h���̂��Ƃ��l���邱�Ƃ�����A���̐l�{���́u���R�Ŗ��ӎ��Ȕ��b�v���������ʂłł��邱�Ƃ�ڎw���܂��B
�u�����Ȕ��b�v��ڎw���̂ł͂Ȃ��A�u�����Ȕ��b�͌��ʓI�Ɍォ��t���Ă���i���ʓI�ɗ����ɘb����悤�ɂȂ�j�v�Ƃ�����������܂��B
���ڔ���w�����̓s�}���v�搶���Ǝ��ɊJ������RASS���_�i���R�Ŗ��ӎ��Ȕ��b�ւ̑k�y�I�A�v���[�`�j�Ɋ�Â��h���P���@�ŁA���꒮�o�m��ΏۂƂ����发�ɂ������Ɏ��グ���Ă��܂��B
�Ԑږ@�ɂ��Ă͎�f���ɏڂ����������܂��B
�����ʂɂ͌l��������܂��B
���Ԑږ@���Â͑������͂���܂���B
�@����āu�����ɃX���X���b����e�N�j�b�N�������ė~�����v�Ƃ������̗v�]�ɂ͓������܂���B
���Ԑږ@���Â͉�����ʉ@���p�����Ă��炤�K�v������܂��B
���@�͈�Ë@�ւł��̂Őf�@���̌l���S�͏����čς݂܂��B�i�f�@���j
�ی��f�Ái�ʏ�3�����S�j�ōs���Ă��܂��̂ŁA�ЂƂ�e�ƒ듙��Ô����q�ǂ���Ô���ȂNJe�����̂̏������x�����p�ł��܂��B
�p�����Ēʉ@�����ꍇ�������x����Ô�i���_�ʉ@�j���x�����p�ł�1�����S�ƂȂ�܂��B
�ڂ����͎�f���ɑ����ł������������B
���S�\�ł��B